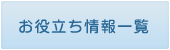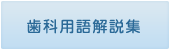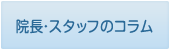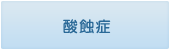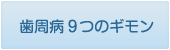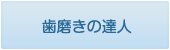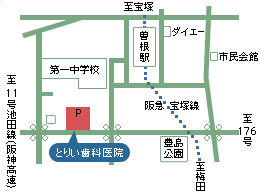院長・スタッフのコラム
- ホーム
- お役立ち情報
- 院長・スタッフのコラム
- 2023年度コラム
2023年12月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その151
Q:口臭って胃から出てくるのですか?
A:× 胃の中のにおいが口臭になることはほとんどありません。口臭の大部分(80%以上)は、お口の中の気体に由来します。口臭には、「生理的な口臭」と「病的な口臭」があります。
「生理的口臭」は起床時、空腹時など、誰にでもある一時的な口臭で、1日のうちに自然に増減します。食べ物や飲み物成分が一過性ににおうというものは時間が経てばなくなるので生理的口臭に含まれません。生理的口臭は健康なひとでも起こるので心配する必要はありません。
一方、「病的口臭」は持続的に発せられるにおいで、原因がなくならない限り続きます。歯周病などのお口の病気や、鼻炎などの鼻咽の病気や糖尿病、肝疾患など全身の病気により起こります。生理的口臭と病的口臭は成分的には違いがなく明確に2つに分けられるものではないですが、強い口臭が続くというのはお口か全身に不調が起きているのかもしれません。
では、口臭の中でよくある歯科的な原因を2つご紹介します。
まず1つ目は、舌苔です。舌苔とは舌の表面に堆積した汚れのことです。舌には細やかな突起(舌乳頭)が無数にあり、そのすき間に、はがれ落ちたお口の粘膜や唾液の成分、食べかすなどが堆積したもので、白色や薄黄色をしています。細菌がそれらを餌にして発するにおいが口臭になります。どれだけ歯をきれいにしていても、舌についている細菌を取り除かないことには口臭の原因になってしまうのです。
予防は、においのもととなる舌苔を落とすために舌の清掃をすることです。方法として、舌ブラシややわらかめの歯ブラシを使って舌の奥から手前に優しく撫でるように動かします。ただし、舌が傷ついてしまうので、力の入れ過ぎやりすぎには注意が必要です。
2つ目は、歯周病です。歯周病は歯ぐきの溝の中にプラーク(細菌の塊)が溜まることで起こります。歯ブラシで溝の中のプラークは自分では完全に取ることができません。プラーク内の細菌が血液、食べかすなどを分解して強いにおいを発します。深い歯周ポケットが短期間で浅くなることはなく治療には時間がかかりますが、しっかりお口の中の環境を整えていけば、においは徐々に減っていきます。
このように、「歯医者さんに行ったら口臭が減った」という方は意外と多いのです。
口臭は歯科治療で劇的に良くなる可能性があります。口臭が少しでも気になるのであれば歯科医院で一度口臭検査を受け原因を調べてみてはいかがでしょうか。
次回のQは・・・・
「ガムを噛むのは健康にいいですか?」です。
歯科助手 木下 彩
2023年11月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その150
Q:洗口液を使ってみようと考えているのですが、どれでもおなじですよね?
A:洗口液によって含まれている殺菌成分が違います。使用するタイミングや使用目的に応じて洗口液を選んでください。
洗口液というのは毎日の歯磨きに加えて使用されるものです。製品に書いてある量を口に含み大体20~30秒ほどすすぎます。同じ棚に並んでいることも多い液体ハミガキとは使用方法が全く違うので、購入する際はラベルに「洗口液」と表示されているか確認してみてください。因みに液体ハミガキは口に含み、口の中全体に行き渡らせたのち吐き出し、そのあと歯磨きをするものです。
まず洗口液を歯周病予防として使用される場合、グルコン酸クロルヘキシジン(CHG)・セチルピリジウム塩化物水和物(CPC)・ベンゼト二ウム塩化物(BTC)これらの成分が入った洗口液がいいです。歯磨きの後に使用することで、バイオフィルム(プラーク)という歯周病菌などの細菌を取り囲んでいるバリアに付着して殺菌します。また、歯の表面に吸着してバイオフィルムが形成されることから守ってくれます。ただ、バイオフィルムの内部に浸透していくことはできないので、歯磨きで物理的に破壊し、その後1~2分以内で使用しましょう。
とはいえ、お昼休みが短くどうしても歯磨きする時間がない時もあると思います。その場合は、エッセンシャルオイル・ポピドンヨードこれらの成分が入った洗口液がいいです。歯みがき前でバイオフィルムを物理的に破壊しなくても洗口液がバイオフィルム内部に浸透して破壊してくれます。ただ、効果を発揮できるのは初期のバイオフィルムで、成熟し厚くなったバイオフィルムには効果が弱いです。前回の歯磨きから5時間以内、遅くとも7時間以内に使用しましょう。
他にも歯ぐきの腫れや炎症を抑える成分としてトラネキサム酸・グリチルリチン酸などの入った洗口液、口臭を抑える塩化亜鉛が入った洗口液などが売られています。
ご自身の使用目的や使用する際の状況を考えたうえで選んでくださいね。
ただ、虫歯リスクが高い方には注意が必要です。虫歯には、フッ素が効果的だということは、知っている方も多いと思います。フッ素入り歯磨き剤を使って磨いた後に洗口液を使用しすすいでしまうと折角のフッ素が流れてしまいます。フッ素は長く口腔内に留めておくことが重要ですので、虫歯リスクが高い方は、さらにフッ素の洗口液を使用するのがいいでしょう。
次回のQは・・・・
「口臭って胃からでてくるのですか?」です。
受付 中村りこ
2023年10月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その149
Q:フッ素入りの歯磨き粉、効果的な使い方なんてあるの?
A:○ 使い方により効果はさらに高まります。
そもそもなぜ虫歯予防にフッ素が効果的なのかというと、1)再石灰化を促す。溶け出した歯の成分のリンやカルシウムが歯の表面に戻るスピードを加速します。 2)歯を硬くする。再石灰化の際、歯を作っている成分ハイドロキシアパタイトにフッ素が加わり、フルオロアパタイトになり硬く酸に溶けにくくなります。 3)虫歯菌の活動を抑える。プラーク内に入り込み虫歯菌が糖から酸を作る力を抑えます。
しかし、フッ素配合歯磨き剤はただ使えばいいというわけではありません。効果を高めるための使い方があるのですが、その前に年齢別の推奨使用量と配合濃度があります。
- 歯が生えてから2歳→900~1000ppmの歯磨き粉を米粒程度(1~2mm)
- 3~5歳→900~1000ppmの歯磨き粉をグリーンピース程度(5mm)
- 6歳~成人・高齢者→1400~1500ppmの歯磨き粉を歯ブラシ全体 (1.5~2cm)
これらの濃度と使用量は有効性が確認されており、かつ安全に配慮されたものです。以前研磨性の高い歯磨き剤が主流であったころは、歯ブラシの半分くらいでいいといわれていましたが、フッ素濃度を上げるにはたくさんめにつける方が効果が上がります。フッ素が配合された歯磨き剤には、成分表に「フッ化ナトリウム」「モノフルオロリン酸ナトリウム」「フッ化第一スズ」などの記載があります。
使用時のコツは、フッ素をいかに口の中に長時間残留させるかということです。
- 1) フッ素配合歯磨き剤は使用回数が多いほど予防効果が高いといわれているので、1日3回するのがいいでしょう。
- 2) 夜の歯磨きは夕食後より就寝前の方が効果があります。就寝中は唾液が減りフッ素が残りやすいのです。
- 3) 歯磨き後のうがいは最小限の少量の水で。できれば1回で済ませましょう。水の代わりにフッ素洗口液を使用するとより効果的です。
- 4) 最初は、奥歯など虫歯になりやすいところから磨きましょう。磨いている間に唾液で薄まっていくからです。
フッ素配合歯磨き剤の効果を高めるために、以上の点に注意して毎日の歯磨きを行ってみてください。
ただし、フッ素入りの歯磨き粉を使っていれば虫歯にならないというわけではないので、定期的にかかりつけの歯医者さんで診てもらいましょう!
次回のQは・・・・
「洗口液を使ってみようと考えているのですが、どれでもおなじですよね?」です。
歯科衛生士 長船瑞稀
2023年9月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その148
Q:歯周病予防のために歯ぐきの溝のなかまで歯ブラシを入れて磨いています。しっかり磨いているので問題ないですよね?
A:×歯ぐきの溝を磨きすぎると弊害が出ることもあります。
歯ぐきの溝(歯周ポケット)のなかは細菌の塊であるプラークが溜まりやすい場所で、溜まったプラークは歯周病の原因になります。また、プラークが溜まり歯ぐきが腫れて出血すると、血管から細菌が入り全身疾患(心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病など)に繋がる恐れもあります。そのため、この部分を清潔にすることは大切で、一生懸命に磨いているかたも多いのではないでしょうか?
しかし、歯ブラシでは溝のなかのプラークは完全には取り切れません!健康な歯ぐきの場合溝の深さは1~2mmで、しかも歯ブラシが届くのは1mm程度です。溝のなかに無理に歯ブラシの毛先を入れて磨くことを続けてしまうと、歯がくさび状に削れて知覚過敏になったり、歯ぐきが傷つきさがってしまい、歯の根面が露出してしまったりする恐れがあるのです。歯の根面は柔らかく虫歯になりやすい部分でもあります。
そのため、歯ぐき周辺を磨くときには歯ブラシを力いっぱい当てずに優しく小刻みに当てましょう。と言っても実際に手を取ってだれかに教えてもらわなければ、力加減もわからず歯ぐきの健康が維持できるように上手に磨くことは難しいです。そこは歯科衛生士にお任せください!歯科医院へ来ていただければ丁寧に指導させていただきます。
一方溝の深さが3mmを超え歯周病になってしまっておられる方の場合、深い部分に存在するプラークや歯石はどうすればいいのでしょうか。ご自分で行うのは無理です。それには歯科医院で歯科医や歯科衛生士が細い器具を溝の奥まで挿入し丹念に汚れを除去する必要があります。これには時間と手間がかかります。場合によってはそのままでは痛みを伴うので痛み止めの注射して、または外科的に歯ぐきを切り開いて処置することもあります。こうして一度深い部分まできれいにしておくと、そう度々深い部分を触る必要はありません。あとは歯ぐきの上の部分をご自分でお手入れしていただくだけで済みます。
因みに歯ぐきの溝の浅い部分については補助的な道具でお手入れが可能ですので、いずれまたお話しさせていただきます。
次回のQは・・・・
「フッ素入りの歯磨き粉に使い方なんてあるの?」です。
歯科衛生士 福井万緒
2023年8月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その147
Q:ガムを噛むのは健康にいいですか?
A:○唾液が多量に出るので唾液の持つ作用と噛むことが全身におよぼす効果によって、健康的になります。
ものを噛むと自然に口の中に唾液があふれてきます。そこでは唾液そのもののチカラと噛むという運動が全身におよぼす効果により、我々の健康は支えられています。ガムはそもそも長く噛むために作られたおやつです。噛んでいる間中唾液は分泌されるので、分泌量を増やすには最適の方法です。
まず今回は唾液のもつチカラについてお話させていただきます。
唾液は単なる水ではありません。溶けているたくさんの成分により様々な機能を発揮します。主な作用を列挙します。
- 潤滑作用
ムチンと呼ばれる糖タンパクが口腔粘膜を滑らかにすることにより咀嚼・嚥下・発語などに際し舌・唇・頬粘膜などの運動を円滑にする作用があります。 - 自浄作用
食物残渣や虫歯・歯周病のもとになる細菌を洗い流します。その後は無意識のうちに嚥下し、口腔内をきれいにします。 - 消化作用
唾液中に含まれる消化酵素アミラーゼによりデンプンをマルトースやグルコースに分解し、栄養を消化吸収しやすくします。 - 食塊形成作用
食物を湿らせることで食塊形成を容易にし、食物を飲み込みやすくします。 - 味覚作用
食物中の味覚物質を溶解することにより、舌の上に行き渡らせ味覚を感じやすくします。 - 抗菌作用
リゾチーム、ラクトフェリン、ペルオキシダアーゼなどの物質が抗菌作用をもっています。また、分泌型免疫グロブリンAが口から侵入する病原微生物の産生する毒素や酵素に対して中和作用を発揮します。 - 緩衝作用
炭酸-重炭酸系により、酸性およびアルカリ性に傾いたpHを中性に戻す働きがあります。食事で酸性に傾き歯が脱灰すると、緩衝作用によりpHが中性に戻ろうとし再石灰化が起こります。
以上のような唾液の効果を引き出すには、多量の唾液を出すことが必要です。同じ噛むおやつの中でも、グミやするめよりガムの方がたっぷり唾液がでることがわかっており、また一度に食べるガムの量が多いほど唾液はよく出ます。当然キシリトール入りガムならむし歯予防にもなります。
噛むという運動が全身におよぼす効果についてはいずれまたお話しします。
次回のQは・・・・
歯周病予防のために歯ぐきの溝のなかまで歯ブラシを入れて磨いています。しっかり磨いているので問題ないですよね?
院長
2023年7月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その146
Q:永久歯の先天欠如と言われました。すぐに治療が必要ですか?
A:先天欠如(せんてんけつじょ)が判明したら、すぐに治療が必要になるとは限りません。しかしながら、現在ある乳歯をできるだけ長く残すために定期的な管理が大切になります。
もし抜けてしまった場合は、矯正治療や人工の歯で補う治療を行います。
まず、永久歯の先天欠如とは、何らかの原因で顎のなかに永久歯が形成されないことをいいます。ヒトの歯は動物としての長い歴史の中で退化傾向にあり、形は小さく、数は少なくなってきています。歯を武器や道具として使うこともなくなり、調理した柔らかいものを食べるようになってきたからでしょう。先天欠如は約10人に1人の割合で見られることが分かっています。上の歯よりも下の歯に先天欠如が起こる場合が多いです。最も多い部位は、下の第二小臼歯(前から5番目の歯)です。
乳歯から永久歯への生えかわりは、永久歯が下から乳歯を押すことによって起こりますが、永久歯が欠如していると乳歯はそのまま残ります。乳歯は永久歯より歯冠も歯根も小さいので、永久歯の代替として一生使うのは難しいですが、できるだけ長く使っていくためには乳歯がむし歯にならないようにセルフケアや定期的な受診による管理が必要になってきます。そして、代替えの乳歯が抜けてしまった後はそのままにしておくと歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があるため、以下のような治療が必要になります。
- 矯正治療・・・歯を移動させることによって先天欠如のある部位を閉鎖する方法です。
学童期より治療が可能です。 - ブリッジ・・・先天欠如の両隣の歯を削って土台を作り、橋渡しするように人工の被せを入れます。成人期に治療を行います。
- インプラント・・・顎の骨に人工歯根を埋め込み、土台を作ります。その上から人工の被せを入れます。歯列の成長が終わった成人期(大体30歳以降)に治療を行います。
- 部分入れ歯・・・両隣の歯を支えにした、取り外しの入れ歯です。成人期に治療を行います。
先天欠如かどうか判断する時期は、一般的な永久歯の歯胚形成時期の7歳以降が目安とされています。パノラマレントゲン検査では、お口の全体を確認することができます。歯ぐきの中にある永久歯の状態などを確認することで、早期発見につながります。
7歳頃を過ぎたら、一度パノラマレントゲン撮影による検査をおすすめします。もちろんすぐに治療ということにはなりませんのでご安心ください。
次回のQは・・・・
ガムを噛むのは健康にいいですか?
歯科衛生士 西迫 典子
2023年6月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その145
Q:子どもがフッ素入りの甘い歯磨き剤をこっそり舐めていたんですが、フッ素の取り過ぎは体によくないですよね?
A:フッ素の摂取には年齢ごとに上限量があり、それを超えていなければ問題ありません。ただ、フッ素の使用は大人の管理が必要です。
フッ素を過剰に摂取した場合、いくつかの副作用が現れることがあります。一度に多量を摂取した場合の急性中毒では、下痢や嘔吐、悪心などの症状がでます。少量を長期に摂取した場合の慢性中毒では「歯のフッ素症」という特徴的な症状が現れます。これは、歯が形成される時期に、高濃度のフッ素の継続的な摂取によって生じる症状で歯の色や形に異常が認められるようになります。
フッ素は人工的に作られた物質ではなく、ほとんどの食物に含まれる栄養素なので塩分などと同じように、過剰に摂取すると問題を引き起こします。フッ素の適正な摂取量は体重1kgあたり1日0.05から0.1mgとされているので、3~5歳の平均体重では1日0.8から1.6mgとなります。それくらいの年齢のお子さんの1回の歯磨きで使用するペーストの量は5mmくらいですので、食物からの摂取量と1日2回分のペーストを全部食べたとしても問題のない量です。
ご存知のようにフッ素は、虫歯予防の方法でも科学的根拠(エヴィデンス)があると認められており、フッ素配合の歯磨き剤の使用はとても重要な虫歯予防法の一つです。歯が生えたての乳幼児から高齢者まで一生を通じて使用することが大切です。
2歳までのお子さんは、ペーストのフッ素の濃度が1000ppmまで、使用量は1~2mm程度の少量で、使用後ティッシュで拭ってあげてもいいです。
3~5歳のお子さんは、フッ素濃度は1000ppmまで、使用量は5mm程度、就寝前が効果的です。使用後、可能な限り吐出します。直後にすすぐ場合はフッ素の効果をおとさないよう少量の水(大さじスプーン1杯程度)で1回のみにします。
6歳から成人・高齢者の方は、フッ素濃度は1500ppm、使用量は1.5~2cm程度で就寝前が効果的です。使用後は同じく可能な限り吐出します。直後にすすぐ場合はフッ素の効果をおとさないよう少量の水(大さじスプーン1杯程度)で1回のみにします。
市販の歯磨き剤のラベルにもフッ素濃度がきちんと表記されているものがあるので、確認して購入されることをお勧めします。
そして、お子さんが歯磨き剤をこっそり舐めているのは大きな問題です。子どもの手の届かない場所に保管しましょう。また、お子さん自身の歯磨きは、歯磨き剤なしの空磨きをし、大人が仕上げ磨きをするときに、適切な量の歯磨き剤を使用するようにしましょう。
次回のQは・・・・
永久歯の先天欠如と言われました。すぐに治療が必要ですか?
歯科衛生士 西迫 典子
2023年5月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その144
Q:毛先が細く加工された歯ブラシと毛先が丸く加工された歯ブラシ、実際どちらがいいのですか?
A:両方使うことをおすすめします。
最近ドラックストアなどでは色々な歯ブラシが並んでいます。種類がたくさんあり、どの歯ブラシが自分に合うものなのか、迷われる方も多いのではないでしょうか。
色々な種類がある歯ブラシの毛先加工は、大きく分けるとテーパー加工されたものとラウンド加工されたものの2つに分けられます。テーパー加工、ラウンド加工のそれぞれの特徴をご紹介します。
まず、テーパー加工の特徴は、しなやかな毛質で毛の先端が細くなっています。ラウンド加工されたものでは届きにくい狭いところや段差、へこみのあるところに毛先が届きやすくプラークが溜まりやすいところに向いています。歯にモノが挟まって気持ち悪い時のお手入れにもピッタリです。磨くときの注意点として「毛先を歯周ポケットに無理やり突っ込んで磨かない」ということです。歯茎が痩せ、歯根が露出し知覚過敏の原因になってしまうからです。歯周ポケット内に届いても1mm程度です。それより深い部分は歯科衛生士の仕事になります。そして次に、ラウンド加工の特徴は、丸くカットされた毛先であり、優しく安全にお掃除できます。歯の広い面や、噛み合わせ面(咬合面)の効率のよいお掃除ができるのが得意です。しかし、テーパー加工とは違い、へこんでいる場所や細かなところのお掃除には向いていません。
以上2つの歯ブラシの毛先加工の特徴をご紹介しましたが、皆さんはどちらのタイプの歯ブラシをお使いでしょうか。気に入った歯ブラシがあるとそればかり使いたくなると思いますが、実はテーパー加工された歯ブラシとラウンド加工された歯ブラシの両方とも使うことが理想です。フロスや歯間ブラシがどうしても苦手な方には特におすすめです。
しかし、歯磨きは毎日するものであり、朝昼晩毎回2種類の歯ブラシを使うのは面倒に思われることでしょう。そこで歯磨きを1日トータルで考えます。朝の忙しい時間はラウンド加工の歯ブラシでザックリと歯面全体を磨き爽快なお口で1日のスタートを切りましょう。昼は仕事や授業の合間にササっと食事をすませる方が多いのではないでしょうか。テーパー加工の歯ブラシで歯間をお掃除しましょう。そして1番大事なのが夜の歯磨きです。夜は就寝前のリラックスタイムにテーパー加工されたものとラウンド加工されたもの両方使い、丁寧な歯みがきをしましょう。
こうして歯磨きを1日トータルで考え、歯ブラシを使い分ける方法をぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうか。
次回のQは・・・・
子どもがフッ素入りの甘い歯磨き剤をこっそり舐めていたんですが、フッ素の取り過ぎは体によくないですよね?
歯科助手 木下 彩
2023年4月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その143
Q:出っ歯になる原因に舌やくちびるが関係しているってホント?
A:くちびるからの力と舌からの力のバランスによっては歯が前に傾き出っ歯になることがあります。
顎の大きさに対し、歯が大きいと歯並びが悪くなることがありますが、それ以外にも舌や唇の力のバランスも影響します。歯は顎の骨に植わっいるので、基本的にはその形に歯が並びますが、まわりの頬、舌、唇などの筋肉に押され、それらの力のつりあった位置に歯は落ち着きます。それぞれの筋肉の出す力は強くありませんが、長時間力がかかっていると歯は動いてしまうのです。前歯は、唇と舌との間に位置するので、両方から加わる力によっては、前にも後ろにも動きます。例えば舌の力が強く、唇の力が弱い場合、舌が前方に前歯を押しやってしまうので次第に歯が動いていき出っ歯になってしまいます。お口をぽかんと開けていたり、くちびるを噛む癖があったり、日常の些細な癖が歯並びを悪くさせる原因になるのです。これから矯正で出っ歯を治そうと考えられている方で、舌の力が強く歯を押す癖があると、思っているほどスムーズに治療が進まなかったり、治療後に以前の歯並びに戻ってしまったりする可能性があります。
この日常的に繰り返してしまう舌の癖をとるためには、舌のトレーニングが効果的です。MFT(口腔筋機能療法)とよばれ矯正治療の際に一緒に行われることも多く、舌の悪い癖をとり、スムーズに矯正治療を進めていくのに大事になってきます。舌のトレーニングには舌の筋力を鍛えるものや、舌の正しい位置を知るための訓練などあり、矯正の装置を装着する前に行うこともあれば、装置の装着と一緒に行うこともあります。因みに安静時の舌の位置は上顎の天井につき,舌先は上の前歯の根元に触れるか触れないくらいです。
トレーニングは、慣れない動きをしていただくので、舌が疲れてしまいますし、繰り返し続けていく必要があるので根気が必要ですが、続けることできれいな歯並びに近づいていきます。また、お子さんの場合は、子どもの頃にお口まわりの筋力のバランスを良くしておくと、あごの骨格の成長に良い影響を与えてくれるので、矯正の先生にすすめられたら、根気強く続けていきましょう。
次回のQは・・・・
歯ブラシの毛先はテーパ加工されたものか、ラウンド加工されているもの、実際どちらがいいのでしょうか?
受付 中村りこ
2023年3月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その142
Q:家族に歯ぎしりしていると言われました。でも痛いところもないし、問題ないですよね?
A:× 歯ぎしりが原因で歯が割れたり、被せ物が壊れたり、顎関節を傷めることがあります。
歯にかかる過剰な力は、歯を傷めてしまう原因になります。それは大きく2つに分けられ、その一つが歯ぎしりです。食事では上下の歯が当たったら口が開くわけですが、歯ぎしりでは当たってそこから噛みだすわけです。歯ぎしりは無意識に行うものですから、力の加減が効かず大変強い力が持続的に歯にかかります。もうひとつは、TCHと呼ばれる「上下の歯を無意識に接触させる癖」です。食事のときや重いものを持つときなど一時的に上下の歯が当たるとき以外、歯は本来離れているものなのです。安静時、唇は閉じて、上下の歯は離れているのが顎の安定した良いポジションです。TCHは弱い力ですが、日中、長時間力がかかり続けるため歯を傷めるだけでなく、顎の筋肉や顎関節にも負担になります。
では、歯に過剰な力がかかると何が起きるのでしょうか。
まずは、歯がすり減り、ひびが入り、さらに歯の根っこが割れることがあります。噛む力に耐えられなくなった歯は根っこが縦に割れてしまいます。神経のある歯では起こりにくいですが、神経をとる治療をした歯は脆くなり、歯根破折のリスクが高くなります。根っこの割れてしまった歯はほとんどの場合抜歯となります。抜歯の原因として、歯根破折は、虫歯、歯周病に次いで多いのです。また歯周病によって障害を受けた歯周組織に過剰な力が加わると骨の破壊がさらに進み、歯周病が悪化してしまいます。
次に被せ物が壊れやすくなります。せっかく治療をして入れた被せ物、中には自費治療でセラミックを入れた方もいらっしゃるでしょう。しっかり歯みがきをして清潔にしていても、歯ぎしりやTCHの癖で被せ物が欠けたり外れやすくなったりしてしまうのです。
過剰な力を減らすには、自身の癖を認識し、「力のコントロール」をしていくことが大切です。日中のTCHなら、歯が接触していると気付いたときに離すことで改善していけます。
夜間の歯ぎしりを完全に止めてしまう方法は現在ありませんが、歯ぎしりをする方は質の良い睡眠を取ること、夜間にマウスピースを装着することで少しでも歯にかかる負担を軽減できます。かかりつけの医院に定期的に通うことで、自分では気づかなかった歯ぎしりや嚙みしめの癖をいち早く発見し、将来歯を失うリスクを減らし、大切な歯を守っていきましょう。
次回のQは・・・・
「出っ歯になる理由に舌やくちびるが関係しているってホント?」です。
歯科衛生士 長船瑞稀
2023年2月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その141
Q:お口も老化をするということだけど、予防はできるの?
A:○ 色々なお口のトレーニングが考案されています。ご自分のお口の老化に気付かれた方は是非トレーニングに取り組んでいただければと思います。
昨年6月号当コラムでお伝えしましたが、年齢とともに全身的な身体機能が老化していくのと同じように、お口の機能も老化していきます。噛む、飲み込む、話すといったお口の機能もからだの筋肉と同じように加齢とともに衰えていきます。特に最近はご高齢の患者さんを診る機会が増え、処置中にむせる方を多く見かけます。手足の大きな筋肉は、筋肉トレーニング(筋トレ、ウエイトトレーニング)をすれば鍛えられるのはわかりますが、お口の周りの小さな筋肉を鍛えるというのは少し理解しにくいかもしれませんが、鍛えることは可能です。前回ご紹介しましたように色々なトレーニング法が考案されていますが、今回はまた別の方法をお知らせします。
-
1.唾液腺マッサージ
加齢や各種の内服薬の副作用により唾液の分泌量が減少します。それにより食物を飲み込みにくくなったり、義歯が吸着しにくくなったり、口臭が強くなったりします。唾液腺マッサージは強制的に唾液を出す方法です。酸っぱいものを思いうかべながら行うと唾液が出やすくなります。とくに食事の前に行うと食事がしやすくなるので、毎食前に行うのがいいでしょう。
①耳下腺(じかせん)
両耳の下より少し前を人差し指、中指、薬指で押さえながら回します。ゆっくりやさしく10回ほど繰り返します。
②舌下(ぜっか)腺(せん)
両親指を立てて、オトガイの裏の顎の下を上へ押さえます。やさしく10回ほど繰り返します。
③顎下(がっか)腺(せん)
両親指を立てて、顎のエラの内側にはめるようにあて、後ろから前へ10回ほど動かします。 -
2.ベロ回し
①口をぎゅっと閉じ、舌を歯と唇の間に入れます。
②歯の表側に沿わせて、上唇→右頬→下唇→左頬を中から外へ押すように一方向にゆっくり大きく10回まわします。
③次に反対方向にもゆっくり大きく10回まわします。 一日3セットを目安に行います。
このトレーニングは、舌根の筋肉が鍛えられ食べ物をのどに送り込む力が強くなります。また口まわりの筋肉も引き締まり、ほうれい線が改善されます。
一人暮らしで一日誰ともしゃべらない方などは、強制的に口やのどの周りを動かす前回、今回のようなトレーニングをして筋肉を鍛える必要があると思います。
昨年3月号の記事を読んで、ご自分のお口の老化に気付かれた方は是非種々のトレーニングに取り組んでいただければと思います
次回のQは・・・・
「家族に歯ぎしりをしていると言われました。痛いところもないし問題ないですよね?」です。
院長
2023年1月号
「歯科 ウソ&ホント」シリーズ その140
Q:知覚過敏の治療、直ぐに症状がおさまらない。どうして治療に時間がかかるの?
A:知覚過敏の治療は「受診してその日のうちに治る」ケースばかりではありません。
知覚過敏の原因は多岐にわたるので、原因を突き止めそれに合った治療をするには時間がかかる場合もあります。
知覚過敏とは以下のような状態をいいます。本来歯の表面は神経(歯髄)と直接繋がっていない
エナメル質で覆われているので痛みは感じませんが、その下にある象牙質には歯髄の神経と間接的に繋がっている構造になっているので、温度変化や機械的な刺激で痛みを感じます。
色々な原因で象牙質が露出すると知覚過敏を起こすようになります。
知覚過敏になりやすい人には、以下の傾向があります。
-
・強い力でゴシゴシ磨く習慣がある。
→強く磨きすぎると歯ぐきが傷つき下がり、歯根が露出します。歯根はエナメル質より柔らかいので削れてしまいます。 - ・就寝中に歯ぎしりや食いしばりをする癖がある。
→上下の歯がこすれエナメル質がすり減り象牙質が露出したり、ヒビ割れの原因になります。 - ・酸性度の高い飲食物を頻繁に口にしている。
→飲食物の酸がエナメル質を溶かし、さらに進むと象牙質が露出します。 - ・逆流性食道炎や過食症で嘔吐の癖がある。
→胃酸が歯を溶かしてしまいます。 - ・歯周病になった、または歯周病の治療をしたあと歯茎がしまった。
→歯周病で歯槽骨がやせている場合、そのぶん歯茎が下がり、歯根が露出します。
このように色々な原因があるので、根本的に治療をしようとすると時間がかかるのです。
最近はTVCMでも「知覚過敏」という単語をよく耳にするようになりました。30~40年前はそれほどポピュラーではありませんでした。上記の原因の中で歯ぎしりや食いしばりはストレスが原因といわれますので、ストレス社会になったため知覚過敏が増えてきたのではないかというのはうなづけます。また日本人は昔より確実に歯をよく磨くようになっているので、間違った磨き方を続けてしまうと知覚過敏が起きてしまうのです。
治療はまず刺激に対する歯髄(神経)の反応を抑える薬剤を、象牙質が露出している場所に数回塗布します。様子を診て症状が改善しないなら、コーティング剤を塗布して、露出した象牙質を封鎖します。それでも症状が緩和されない場合は、歯根を歯茎で覆う歯周外科手術や強く噛んでいる歯の噛み合わせを調整する、また、神経を抜く「抜髄」もありますが、歯の寿命を損ないますのでどうしても治らないときの最終手段として行います。
また歯磨きの習慣や食生活は意識すれば改善が可能です。歯ぎしりや食いしばりの癖があるかどうかは歯科で診てもらうことでわかります。必要に応じてナイトガードを使用していただくと、就寝中の歯へのダメージが軽減されます。日常的に手軽に取り入れやすい事として、知覚過敏を抑える成分(高濃度フッ素と硝酸カリウム)の入っている歯磨き剤の使用もお勧めです。
しかしながら、一旦知覚過敏が収まっていても悪習慣がもどると、また再発することはよくあります。
次回のQは・・・・
「お口も老化するということだけど、予防はできるの?」です。
歯科衛生士 西迫 典子